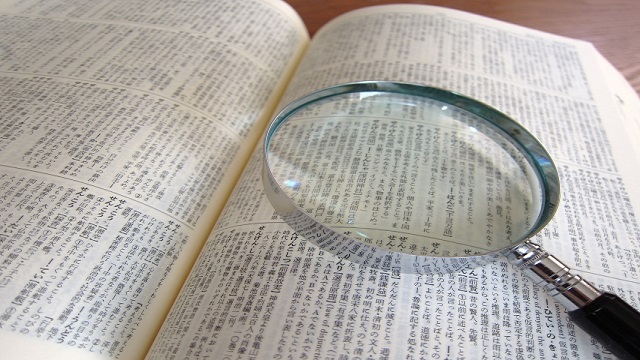井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
「井の中の蛙大海を知らず」の意味
知識、見聞の狭いことのたとえ。世間知らず。
「井の中の蛙大海を知らず」の語源・由来
「井の中の蛙大海を知らず」の語源は、「荘子」秋水篇にある、以下の故事が由来になっています。
昔、黄河という大きな川に、河伯(かはく)という神様がいました。
ある日、河伯は、初めて北海という海に行きました。
その北海には、若(じゃく)という神様がいました。
海の広さに驚いた河伯は、若に「今まで黄河が一番大きいと思っていたのに、こんなに大きいものがあるとは知らなかった。」と言いました。
これを聞いた若は、河伯に言いました。
井戸の中の蛙に、海のことを話しても分からない。
それは、その蛙が狭い井戸の環境にとらわれているからだ。
夏の虫に、氷のことを話しても分からない。
それは、その虫が夏以外の季節を知らないからだ。
見識の狭い人に真理を話しても分からない。
それは、その人がありきたりの教えに縛られているからだ。
今、あなたは狭い川から出て大きな海を見た。
それによって自分自身が無知であったことを知った。
あなたは、これから大きな真理について語ることができるようになったのです。