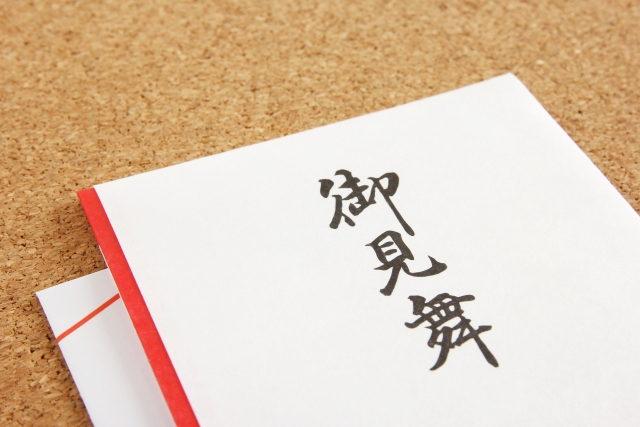訃報を聞いた際に、遺族を訪ねて、お悔やみを述べるのが、弔問(ちょうもん)です。
通夜や葬儀に参列して、弔いの意を表しますが、弔問の際には、遺族に配慮して、失礼にならないように心がけることが大切です。
仏式の場合の、弔問に関しての、基本的なマナーを紹介します。
弔問マナー
亡くなったという知らせを受けたら、まずは場所を確認して、できるだけ早くお悔やみに駆けつけるようにしますが、親族や特別親しかった場合を除いては、通夜前は避けて、通夜や告別式に参列するようにします。
本来、通夜は遺族や親しい人が故人との最後の夜を過ごすもの、葬儀は故人を葬るために行われる宗教的な儀式、告別式は故人と縁のある人がお別れをするための式です。
最近では、葬儀と告別式を一連の流れで行う「葬儀・告別式」というスタイルが一般的になっていますが、故人とそんなに親しくなかった場合には、告別式に出席するというのが本来です。
弔問のタイミングは、
1.すぐに駆けつける(通夜の前)
2.通夜
3.葬儀
4.告別式
の4つがあり、故人と親密であったほど、数字の若いタイミングで弔問し、基本的には、それ以降の全てに参列します。
しかし、最近では、通夜と告別式の意味合いが曖昧になってきていて、昼間に行われる告別式には都合がつかないため、夕刻に行われる通夜にだけ参列するということも、一般化しています。
すぐに駆けつける場合のマナー
突然の訃報を受けて、弔問に駆けつける場合には、平服で良いとされていますが、ちょっとした配慮で、より弔問にふさわしい服装にすることができます。
職場から直行する場合、男性ならビジネススーツのままで構いませんが、できればネクタイは地味なものに、女性も通勤着のままで良いとされますが、アクセサりー類をはずして、派手な化粧は控えるようにするのがマナーです。
自宅から弔問に行く場合は、紺やグレーなどのダーク系のスーツやワンピースなどが無難です。
喪服を着て行くと、用意が良すぎるということで、失礼にあたるとされているので、注意しましょう。
また、駆けつける際には、香典は持って行きません。
香典は、通夜か告別式で渡すようにします。
玄関先で失礼する
弔問に駆けつけた際には、玄関先でお悔やみを伝えて帰るようにします。
家の中へは、遺族にすすめられた場合にのみ入ります。
故人に一目会いたいと思っていても、自分から対面を申し出るのは控えるのがマナーです。
逆に、故人との対面をすすめられた場合でも、気が進まない時には「辛すぎるので」などといって、対面を断っても失礼にはあたらないとされています。
故人との対面の仕方
1.故人の枕元に正座をし、両手をついて一礼する。
2.遺族が白布をとったら、故人の顔を軽く見てお別れをする。この時、遺体には触れないようにする。
3.仏式の場合は、合掌して一礼する。
4.座ったまま少し下がり、遺族に一礼してから、その場を離れる。
通夜でのマナー
通夜は、本来、遺族やごく親しい人が集まって、故人との最後の一夜を過ごすもので、以前は、夜を通して一晩中行われていました。
しかし、今では、午後6時~7時頃から始まって、2時間前後で終わる「半通夜」が、一般的になっています。
通夜での服装も、すぐに駆けつける場合と同様に、平服で良いとされていますが、急でない限りは、葬儀・告別式と同様に、準喪服のブラックスーツを着用するのが一般的になっています。
受付を済ませた後、案内にしたがって会場内に入りますが、祭壇に近い方が、遺族や親族の席になっています。
通夜での弔問手順
1.受付でお悔やみのあいさつをする。
2.香典をふくさから取り出して、両手で差し出す。
3.芳名帳に、楷書で丁寧に記帳する。
4.会場内に進み、指定された場所に座る。
5.焼香の順番になったら、霊前に進んで、遺影に一礼してから、焼香をして合掌する。(受付がなかった場合は、ここで香典を供える。)
通夜の流れ
1.遺族、親族、参列者が着席。
2.僧侶が入場し、読経が始まる。
3.焼香。焼香は、喪主、遺族、親族、友人・知人の順に行われます。
4.僧侶の法話。
5.喪主のあいさつ
6.(通夜振る舞い)
通夜振る舞い
通夜が終わった後、参列者に簡単な食事が振る舞われることがあります。
「通夜振る舞い」と呼ばれますが、これは、故人を偲ぶ場として提供されるもので、故人とともにする最後の食事になります。
通夜振る舞いへの参加範囲は、地域によって異なっていて、関東地方では、一般参列者も含めて通夜振る舞いに参加することが多いようですが、関西地方では、遺族や親族のみで通夜振る舞いを行うことが多いようです。
基本的には、その地域のしきたりに合わせるようにしますが、遺族から参加をすすめられたら、できるだけ参加するようにしましょう。
通夜振る舞いでは、料理に箸をつけることが、供養になるとされているので、席についたら、一口だけでもいただくのがマナーになります。
また、通夜振る舞いは、故人を偲んで話をする場なので、故人に関係のない話は避けるというのも、大切なマナーです。
通夜振る舞いは、1時間程度行われることが多いですが、故人や遺族と親しい間柄でなければ、あまり長居はせずに、早々に引き上げるようにしましょう。
葬儀・告別式でのマナー
本来、宗教的な儀式である「葬儀」と、故人にお別れをする「告別式」とは、別の意味を持つものでしたが、現在では、葬儀と告別式を一連の流れで行う「葬儀・告別式」というスタイルが一般的になっています。
一般の弔問者も、葬儀・告別式に最初から参列するというのが、通例となっています。
葬儀・告別式での服装
遺族や近親者は、正式な喪服を着用しますが、一般の弔問者は、それよりも格を下げた「準喪服」を着用するのがマナーとされています。
男性の服装
服:準喪服。シングルまたはダブルのブラックスーツ。濃紺やダークグレーのスーツでも良いとされています。
ネクタイ:黒色。ネクタイピンはシルバーが無難です。
シャツ:白無地のワイシャツ
靴:光沢のない黒色。靴下も黒に揃えます。
アクセサリー:時計やアクセサリー類ははずしますが、結婚指輪はつけていても良いとされています。
女性の服装
服:準喪服。黒色のスーツ、ワンピース、アンサンブルなど。紺色やグレーなども良いとされています。
化粧:薄化粧にして、アイシャドウはブラウンやグレー系に。口紅も控えめな色にしますが、香水はつけません。
靴:黒色のパンプス。サンダル、ブーツなどは適しません。
ストッキング:無地の黒色。ナチュラルベージュでも良いとされています。
アクセサリー:パールやオニキスなどの一連のネックレス。ネックレスをつけてはじめて正装となります。
子供の服装
制服が、喪服がわりになります。
制服がない場合は、黒、紺、濃いグレーのブレザー、スボン、ワンピース、スカートなどにして、靴は革靴にします。
葬儀・告別式の流れ
1.遺族、親族、参列者が着席。
2.僧侶の入場
3.開式
4.読経
5.弔辞・弔電披露
6.焼香。焼香は、喪主、遺族、親族、友人・知人の順に行われます。
7.僧侶の退場
8.閉式
焼香のマナー
仏式の葬儀では、香りで霊前を清めて故人の冥福を祈るために、焼香が行われます。
焼香は、立って行う「立礼(りゅうれい)焼香」と、座って行う「座礼焼香」がありますが、会場が狭い場合には「回し焼香」が行われることもあります。
また、粉末状の「抹香」ではなく、棒状の「線香」を手向ける「線香焼香」の場合もあります。
焼香は、抹香を香炉に落とすのが一般的な方法です。
落とす回数は、宗派によって1回~3回と異なりますが、弔問客が多い場合には、時間を短縮するために、1回焼香を指示されることもあります。
立礼焼香の手順
1.遺族と僧侶に一礼した後、祭壇の前まで進み、遺影に一礼する。
2.焼香台まで進み、親指、人差し指、中指で抹香をつまみ、軽く頭を下げるようにして、目の高さまで持ち上げる。
3.香炉の火の周りに、静かに抹香を落とす。
4.合掌し、一歩下がって遺影に一礼する。
5.僧侶と遺族に一礼して席に戻る。
座礼焼香の手順
1.中腰で前に進み、正座して、遺族と僧侶に一礼する。
2.祭壇の正面に座り、遺影に一礼する。
3.にじるようにして座布団に座り、立礼焼香の要領で焼香する。
4.合掌し、座布団からにじりおりて、遺影に一礼する。
5.僧侶と遺族の方を向き直して、一礼してから席に戻る。
回し焼香の手順
1.香炉が回ってきたら、「お先に」という意味をこめて、次席の人に目礼する。
2.香炉を自分の正面に置き、遺影に一礼してから、立礼焼香の要領で焼香する。
3.祭壇に向かって合掌してから、香炉を次の人に回す。
線香焼香の手順
1.遺族と僧侶に一礼した後、祭壇の前まで進み、遺影に一礼する。
2.右手で線香を1本持ち、灯明(とうみょう)で火をつける。
3.線香を左手に持ち替えて、右手であおって、線香の火を消す。息で火を吹き消すのは禁物です。
4.線香を右手に持ち替えて、香炉に立てる。
5.合掌し、一歩下がって遺影に一礼する。
6.僧侶と遺族に一礼して席に戻る。
香典のマナー
香典は、宗旨によって、使用する不祝儀袋が違ってきます。
宗旨が分からない場合は、無地で「御霊前」と書かれたものを使うようにします。
蓮の花の模様が入った不祝儀袋は、仏式でしか使うことができないので、注意しましょう。
香典には、お金がかかる葬儀に対する相互扶助的な意味合いもあるとされているので、香典の金額に迷った場合には、少し多めに包むのが良いとされています。
夫婦で参列する場合も、香典は一つで、金額も二人分にする必要はありません。
香典の金額は、職場関係なら3千円~5千円程度、親しい友人・知人の場合は5千円~1万円程度、親戚の場合は1万円~3万円程度が目安になります。
香典の表書きなどを書く場合は、「涙で墨も薄まる」という意味から、「薄墨」を使うという風習があります。
仏式の不祝儀袋
表書き:「御香典」「御香料」「御佛前」「御霊前」など
水引き:「黒白」または「双銀」の結び切り
柄:無地、蓮の花
神式の不祝儀袋
表書き:「御榊料」「御神饌料」「御玉串料」「御神前」「御霊前」など
水引き:「黒白」または「双白」もしくは「双銀」の結び切り
柄:無地
キリスト教式の不祝儀袋
表書き:「御花料」「御ミサ料」「御霊前」など
水引き:なし
柄:ユリの花、十字架など
無宗教の不祝儀袋
表書き:「御霊前」
水引き:「黒白」または「双銀」の結び切り
柄:無地